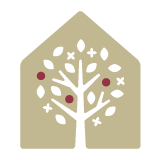ジェイ・ヘイリー ミルトン・エリクソンより学ぶ
1950年代の当時、ヘイリーは、著名な人類学者であり言語学者であるグレゴリー・ベイトソンの
研究チームでコミュニケーションと精神疾患の関係について研究していました。
ベイトソンは、エリクソンの非凡な才能を高く評価しており、1953年にヘイリーがエリクソンの
セミナーへの希望を伝えるとベイトソンは、セミナーへの出席の手はずを取ってくれたそうです。
ヘイリーは、従来の精神療法とは異なるエリクソンの型破りな治療法に興味を持っていました。
エリクソンは、催眠を用いた治療や、患者に直接的な指示を与えるのではなく、
間接的な暗示によって変化を促すなど、独自の治療法を実践していました。
ヘイリーは、エリクソンの治療法の有効性と革新性に惹かれ、彼から直接学ぶことを決意したのです。
また、ヘイリーは、個人の問題を家族全体の文脈で捉える家族療法に関心を持っていました。
エリクソンは、家族療法のパイオニア的存在であり、個人の問題を解決するために
家族全体のコミュニケーションパターンの変化を利用した先駆けでした。
ヘイリーは、エリクソンから家族療法を学ぶことで、自身の研究を深めたいと考えていました。
師弟関係を超えた絆
ヘイリーは、エリクソンの治療法に魅了され、彼の下で学びました。
エリクソンの革新的な催眠療法とコミュニケーション技法は、ヘイリーに大きな影響を与え、彼の治療アプローチの基礎を築きました。
二人は共同で研究を行い、エリクソンの治療事例を分析し、その技法を体系化しようと試みました。
その成果は "Uncommon Therapy"(アンコモンセラピー) という共著として出版され、エリクソンの治療法を理解する上で重要な文献となっています。
エリクソンの影響を受けたヘイリーの家族療法
ヘイリーは、エリクソンの影響を受けつつも、独自の家族療法を開発しました。
エリクソンは1834年、33歳の時に最初の妻と離婚しました。
3人の子供を引き取ったエリクソンは、1936年に再婚しています。
その後、エリクソン一家はさらに5人の子供に恵まれ大家族となりました。
エリクソンは家族との生活を大切にし、エリクソンの成長は家族の成長と共にありました。
エリクソンの家族の意義に対する認識は、1940年代から1950年代にかけての
彼の革新的な仕事を生み出しています。
つまり、エリクソンはセラピーにおいて、家族の利用を試みて問題を解決し
個々の幸福を促進しようとした最初のセラピストだったのです。
そのエリクソンにヘイリーは学び影響を受けたのです。
とは言ってもヘイリーはエリクソンをただ真似ただけではありませんでした。
どちらかというとエリクソンは家族の中での個人に焦点を当てていたのに対し、
ヘイリーは家族全体の相互作用を重視しました。
これは、ヘイリーがエリクソンの治療法を単に模倣するのではなく、
独自の視点で発展させたことを示しています。
具体的には、ヘイリーは、家族システムという概念を重視しました。
これは、家族を個々の成員の集合体として見るのではなく、
相互に影響し合うひとつのシステムとして捉える考え方です。
ヘイリーは、家族システムの中で、個々の成員がどのように振る舞い、
互いにどのように影響し合っているのかを分析し、問題の解決を目指しました。
例えば、ある家族において、子供が非行に走ったとします。
エリクソンであれば、その子供本人に対し、催眠療法などを用いて
内面に働きかけ、問題行動の改善を図るかもしれません。
一方、ヘイリーは、その子供だけでなく、両親や兄弟姉妹を含む
家族全体との関わりの中で、問題行動が生じていると捉えます。
そして、家族全体のコミュニケーションパターンや役割分担などを分析し、
家族システム全体の変化を促すことで、問題の解決を目指します。
このように、ヘイリーは、エリクソンの個人中心のアプローチを、
家族システムという視点から発展させ、独自の家族療法を確立したのです。
さらに、ヘイリーは、家族療法においても、エリクソンから学んだ
間接的なコミュニケーション技法を活用しました。
例えば、家族に対して、直接的な指示や助言を与えるのではなく、
比喩や物語などを用いて、家族が自ら問題に気づき、変化を起こせるよう促しました。
このように、ヘイリーは、エリクソンの治療法のエッセンスを抽出し、
家族療法という新たな枠組みの中で、独自の発展を遂げたと言えるでしょう。
ヘイリーが受け継いだエリクソンの技法
✓間接的なコミュニケーション: 比喩や物語、暗示などを用いて、クライアントの無意識に働きかける方法。
✓抵抗の利用: クライアントの抵抗を、問題解決のための資源として捉え、治療に活用する方法。
✓変化への焦点: 過去よりも現在と未来に焦点を当て、クライアントの変化を促す方法。
これらの技法は、ヘイリーの治療において重要な役割を果たし、多くのクライアントを救うことに貢献しました。
比喩・物語を用いた事例
ヘイリーが家族に対して、比喩や物語を用いて間接的に働きかけた例として、以下のようなものがあります。
例:夫婦間の対立を解消するために「陶芸家の物語」を用いる
ある夫婦が、些細なことで口論を繰り返すという問題を抱えていました。
夫は妻に対して「もっと家事をきちんとやってほしい」と不満を抱き、
妻は夫に対して「もっと自分の気持ちを理解して寄り添ってほしい」と不満を抱いていました。
ヘイリーは、この夫婦に対して、直接的な助言をするのではなく、ある陶芸家の物語を語りました。
物語の概要
昔々、ある村に、腕の立つ陶芸家がいました。
彼は、美しい壺を作ることに情熱を注いでいましたが、なかなか満足のいく作品を作ることができませんでした。
ある日、彼は、森の中で不思議な老人に出会い、壺作りの秘訣を尋ねました。
老人は、
「土と対話することだ」と答えました。
陶芸家は、老人の言葉を理解できずにいましたが、言われた通りに、土と向き合い、
対話するように壺作りを始めました。
すると、今までにない素晴らしい作品が完成したのです。
陶芸家は、土と対話することで、土の性質を理解し、それに合わせて自分の技術を調整することができたのです。
物語の解釈と効果
ヘイリーは、この物語を夫婦に語り聞かせた後、次のように問いかけました。
「この物語は、あなたたちの夫婦関係について、何か示唆を与えていると思いませんか?」
夫婦は、それぞれに物語を解釈し、自分たちの問題に置き換えて考え始めました。
夫は、陶芸家のように、妻の気持ちを理解しようとせず、一方的に自分の要求を押し付けていたことに気づきました。
妻は、土のような柔軟さをもって、夫の気持ちを受け止め、それに合わせて自分の行動を調整することが大切だと気づきました。
このように、ヘイリーは、比喩を用いることで、夫婦が自ら問題に気づき、解決策を見出すことができるよう促しました。
直接的な指示や助言を与えるのではなく、間接的に働きかけることで、夫婦は自分たちで
解決策を見つけ出すことができ、より主体的な変化を促すことができたのです。
ポイント
比喩や物語は、クライアントの抵抗を和らげ、無意識に働きかけることができるため、変化を促す上で有効な手段となります。
ヘイリーは、エリクソンから学んだ間接的なコミュニケーション技法を、家族療法においても効果的に活用しました。
このように、ヘイリーは、エリクソンの影響を受けながらも、独自の視点と創造性を活かして、家族療法を発展させていったのです。
まとめ
ジェイ・ヘイリーは、ミルトン・エリクソンから多大な影響を受け、彼の治療法を基盤に独自の家族療法を確立しました。二人の関係は、師弟関係を超えた、深い絆で結ばれていたと言えるでしょう。
参考文献
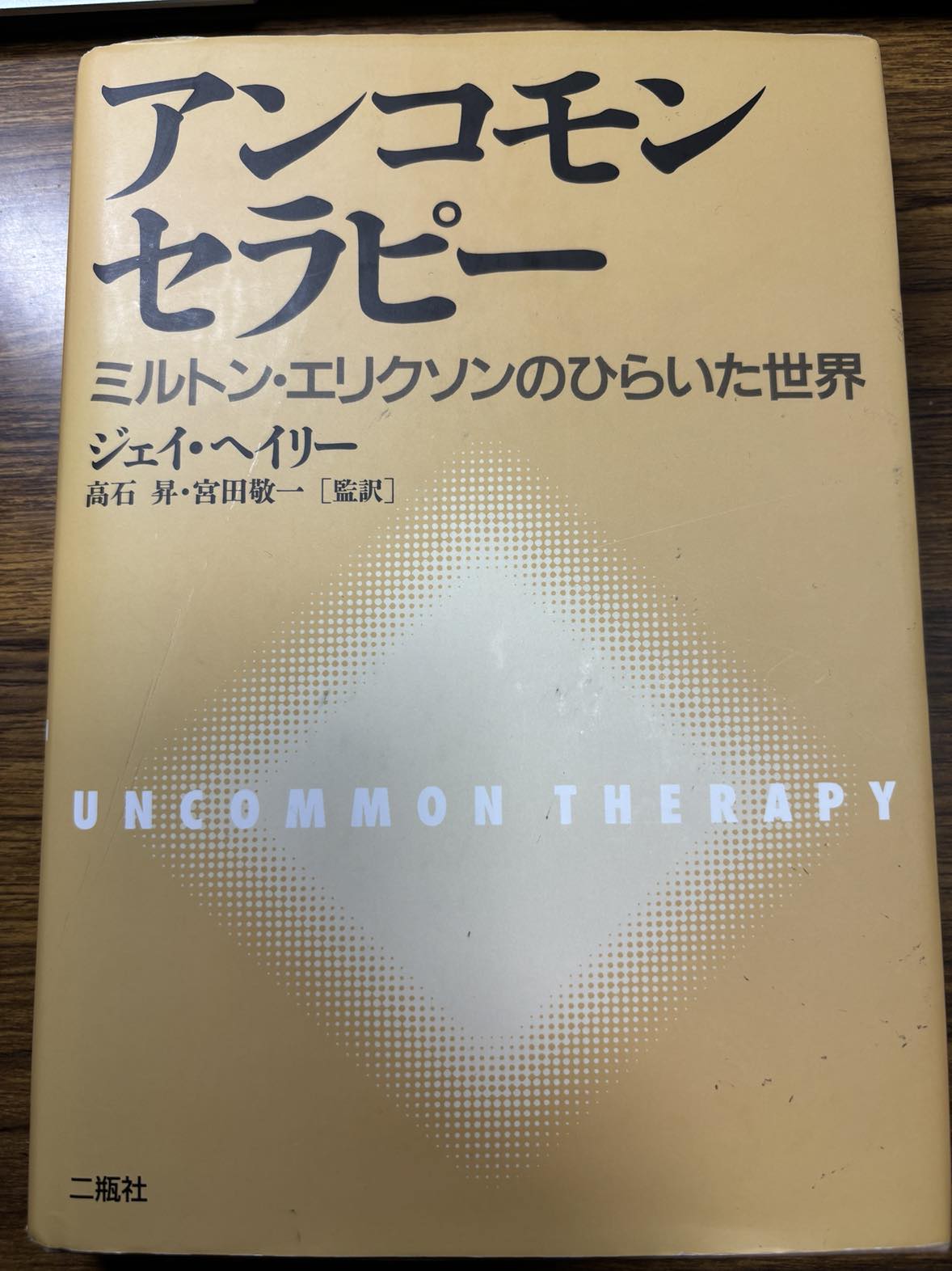
ヘイリー, J. (2001). アンコモンセラピー―ミルトン・エリクソンのひらいた世界. 岩崎学術出版社.
ヘイリー, J. (1997). ミルトン・エリクソンの催眠療法 個人療法の実際. 誠信書房.
この記事が、エリクソンとヘイリーの関係、そして彼らの功績を理解する上で、少しでもお役に立てれば幸いです。