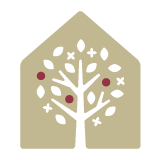ポスト構造主義フーコー 言説(ディスコース)とは
フーコーの言説(ディスコース)の概念は、彼の思想の中核をなす重要な概念であり、
ナラティブ・セラピーに大きな影響を与えました。
言説(ディスコース)とは
簡単に言うと、フーコーにとって言説とは
『特定の時代や社会において、あるテーマについて語ることのできる言葉、概念、表現の総体』
です。
時代や社会によって、ある物事の内容が、どのような言葉や
概念や表現で語られるかは変わってくる、と考えます。
例えば、「精神疾患」について考えてみましょう。
現代では、精神疾患はストレス等の環境要因、脳の機能障害や
遺伝的要因など、生物医学的な視点から語られることも多いでしょう。
しかし、中世ヨーロッパでは、精神疾患は悪魔憑きや
神の罰といった宗教的な言説で語られていました。
このように、同じ「精神疾患」というテーマでも、
時代や社会によってそれを語る言説は大きく異なります。
そして、その言説が、人々の認識や行動、社会制度、権力関係などを
規定していくというのがフーコーの主張です。
もう少し言説について例を挙げてみます。
「昔の人は、病気は悪い霊の仕業だと考えていたけど、
今はウイルスや細菌が原因だと考えているのが一般的だよね。
このように、時代によって病気の説明の仕方が違うのは、言説が違うからなんだ。」
と言説を使うことができます。
あなたは、地球が丸いことを、どのようにして知りましたでしょうか?
昔の人は、地球は平らだと考えていました。
大航海時代よりも昔、船乗りたちは、地球が平らだと信じていたので、
海の果てまで行くと、滝のように落ちてしまうと恐れていました。
なぜ、考え方が変わったのでしょうか?
そうです。 言説が変わったからです。
どうでしょう。
言説がどのような概念か、わかるのではないでしょうか?
フーコーの言説分析
フーコーの言説分析では、以下の点が重要視されます。
言説の規則性
ある言説において、どのような言葉や概念が使用され、
どのような論理や構造で語られるのか、その規則性を明らかにします。
言説の排除
ある言説が成立する過程で、どのような言葉や概念が
排除され、沈黙させられてきたのかを明らかにします。
権力との関係
言説は、権力と密接に結びついています。
ある言説が支配的になることで、特定の知識や
価値観が正当化され、権力構造が強化されます。
主体の構成
言説は、私たちが自分自身や世界を理解する
枠組みを提供し、私たちの主体性を形成します。
ナラティブセラピーにおいての言説の概念
ナラティブセラピーにおいての言説の概念は、以下のような点で重要です。
問題は社会的に構築される
問題は、個人の内面に存在するものではなく、
社会的な言説によって構成されるという視点が強調されます。
権力からの解放
支配的な言説に疑問を投げかけ、クライアント自身の
物語を創造しなおすことで、権力関係から解放されることが目指されます。
新たな可能性の創出
既存の言説にとらわれず、新たな言説を創造することで、
クライアントの自己理解を深め、新たな可能性を開くことが促されます。
具体例「外在化」
具体例として、ナラティブセラピーにおける「外在化」の手法を考えてみましょう。
クライアントが「私はダメな人間だ」という問題を抱えているとします。
これは、「自己責任」や「能力主義」といった現代社会の
支配的な言説に影響された自己認識と捉えることができます。
そこで、セラピストは「ダメな人間」という言説をクライアントから切り離し、
「ダメな人間」という考え方がクライアントを苦しめている、というように問題を外部化します。
これにより、クライアントは「ダメな人間」という言説に支配されるのではなく、
その言説と距離を置くことができます。
そして、自分自身の物語を語り直し、新たな自己像を
創造していくことが可能になります。
まとめ
フーコーの言説の概念は、ナラティブセラピーにおいて、問題を社会的な文脈で
理解し、クライアントのエンパワメントを促進するための重要な理論的基盤を
提供しています。
更に探求するための文献
「知の考古学」(河出文庫)ミシェル・フーコー(著)槙改康之(訳)