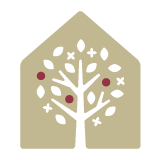ナラティブ・セラピーに影響を与えた思想 社会構成主義
このサイトの管理人です。当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
情報がお役に立てれば幸いです。
マイケル・ホワイトとデヴィッド・エプストンは、様々な思想を柔軟に取り入れて
ナラティブ・セラピーを形作っていきました。
ナラティブ・セラピーへの影響が大きかったと思われるのが
グレゴリー・ベイトソン、社会構成主義及びポスト構造主義です。
ここでは、その一つ社会構成主義がどのようにナラティブ・セラピーに
影響を与えたのかについて、概要をまとめます。
1.社会構成主義とは
社会構成主義は、現実や知識が「客観的」または「独立的」に存在するのではなく、
社会的な相互作用や文脈を通じて構築されるという考え方です。
私たちが「現実」として認識するものは、個人によってではなく、
社会全体の言語、文化、価値観、関係性によって形成されています。
2.社会構成主義の基本的な特徴
現実は構築される
現実は「既にあるもの」ではなく、人々のコミュニケーションや相互作用によって作られると考えます。
たとえば、社会的なルールや常識は絶対的なものではなく、歴史的・文化的に変化します。
言語が中心的役割を果たす
言語は、現実を構築する主要なツールとされています。「言葉」そのものが、
私たちの世界観や体験の枠組みを形作るからです。
例: 「成功」の定義は文化や時代によって異なるように、言葉を通じてその意味が作られます。
知識は文脈依存
知識や真実は固定されたものではなく、時代や文化、文脈によって異なります。
このため、どの視点も相対的であると考えます。
個人ではなく関係性を重視する
個々の「私」が持つ感情や信念さえも、
社会的な文脈や他者との関係の中で
形成されると考えます。
3.ナラティブセラピーとの関連
社会構成主義の視点は、ナラティブセラピーの基本概念と強く結びついています。
「物語」による現実の構築
私たちが自分や人生について抱く物語は、社会的文脈によって影響を受けます。
例えば、
何が「成功」か、「問題」とみなされるかは、社会や文化による枠組みに基づきます。
外在化(Externalization)の手法
ナラティブセラピーでは、問題を「人」ではなく「外部」にあるものとして位置づけます。
(例: 「不安」という問題が私の人生を妨げている)
この考え方は、「問題」そのものも社会的な物語の産物であるという
社会構成主義の見解の影響を受けています。
多様な真実の存在
社会構成主義では、一つの固定された真実はなく、
複数の解釈が可能であるとします。
同様に、ナラティブセラピーでは、クライアントが既存の物語を見直し、
新しい物語を作るプロセスを支援します。
具体例
社会構成主義の視点を考慮したセラピー
例: Aさんが「私は劣っている」という自己評価を持っている場合。
社会構成主義的視点では、この自己評価がAさん自身の中に
「本質的に」あるわけではないと考えます。
その信念は、家庭や学校、職場、メディアなどの社会的な
メッセージの中で形作られたものである可能性があります。
ナラティブセラピーでは、Aさんが
「どんな場面で誰からその考えの影響を受けたのか」
「それに代わる物語は何か」
を探求できるプロセスを提供します。
4.主要な思想家
ピーター・バーガーとトーマス・ルックマン
彼らの著書「現実の社会的構成ー知識社会学論考」は、
社会構成主義の重要な基礎を築きました。
この中で、知識がどのように社会的に構築されるかを詳述しています。
ケネス・ガーゲン(Kenneth J. Gergen)
社会構成主義の心理学的側面を広めた人物です。
彼は、人々のアイデンティティも社会的相互作用による産物であると提唱しました。
ヴィゴツキー
彼の社会構造主義は学習における社会的な相互作用の重要性を強調しており、
ナラティブ・セラピーにおける協働的な関係性に影響を与えたと考えられます。
5.社会構造主義のセラピーへの適用の限界とナラティブ・セラピー
〈限界1〉 客観的な真実の軽視について
社会構成主義は、すべての知識や真実は社会的に構築されると
主張するため、客観的な真実は存在しない、あるいは重要ではない
という立場をとることがあります。
しかし、セラピーにおいては、クライアントの抱える問題が、社会的な
影響を受けていると同時に、生物学的な要因や個人的な経験なども
複雑に絡み合っている場合が多いです。
そのため、社会的な側面のみを強調しすぎると、他の重要な要因を
見落としてしまう可能性があります。
例えば、精神疾患の原因を社会的な要因にのみフォーカスしてしまう
危険性を生じる可能性があります。
【限界1へのナラティブ・セラピーのスタンス】
ナラティブセラピーは、クライアントの主観的な経験を重視しますが、
客観的な真実は存在しないという極端な立場はとっていません。
むしろ、クライアントが自身の経験を語る中で、新たな意味や
解釈を見出し、より豊かな物語を創造していくことを支援しています。
その過程において、セラピストは、クライアントの物語に共感しつつも、
客観的な視点も持ち合わせ、多角的な視点からクライアントを
支援することを心がけています。
〈限界2〉 個人の責任の軽視
社会構成主義は、個人の行動や思考も社会的な文脈によって
規定されると考えるため、個人の責任を軽視する傾向があります。
しかし、セラピーにおいては、クライアントが自身の行動や思考に
対して責任を持ち、主体的に変化していくことが重要です。
社会的な影響を強調しすぎることで、クライアントが自身の責任を
回避したり、変化へのモチベーションを失ってしまう可能性も懸念されます。
【限界2へのナラティブ・セラピーのスタンス】
ナラティブセラピーは、クライアントが社会的な影響を受けていることを
認識しつつも、クライアント自身の主体性や責任を重視しています。
問題を外在化することで、クライアントが問題に飲み込まれることなく、
主体的に問題に対処できるよう支援しています。
また、クライアントが自身の物語を再構築する過程において、
自己責任や自己決定を促し、エンパワメントを目指しています。
〈限界3〉 文化相対主義に陥る可能性
社会構成主義は、文化や社会によって異なる価値観や規範を
認めることを重視するため、文化相対主義に陥る可能性があります。
文化相対主義とは、すべての文化や価値観は等しく尊重されるべきであり、
優劣をつけることはできないという考え方です。
しかし、セラピーにおいては、クライアントの文化や価値観を尊重しつつも、
倫理的な観点や社会的な規範を考慮する必要があります。
例えば、虐待や暴力といった行為は、文化や社会によっては未だに容認されている
ケースもありますが、セラピーにおいては、そのような行為を容認することはできません。
【限界3へのナラティブ・セラピーのスタンス】
ナラティブセラピーは、クライアントの文化や価値観を尊重することを重視しますが、
文化相対主義に陥ることを避けるため、倫理的な指針を設けています。
例えば、虐待や暴力といった行為は、いかなる文化においても容認される
ものではないと考え、セラピストは、クライアントの安全と福祉を最優先に
行動する必要があります。
また、セラピスト自身の文化や価値観が、クライアントへの介入に影響を
与えないよう、自己認識を高め、偏見や差別をなくす努力を続ける必要があります。
〈限界4〉 変化への抵抗
社会構成主義は、既存の社会構造や権力関係を批判的に捉えるため、
変化への抵抗を生む可能性があります。
セラピーにおいては、クライアントが自身の抱える問題を社会的な文脈で理解し、
新たな視点や可能性を見出すことが重要です。
しかし、社会構造や権力関係に目を向けすぎることで、
クライアントが現状を変えることに対して無力感や抵抗を
感じてしまう可能性も考えられます。
【限界4へのナラティブ・セラピーのスタンス】
ナラティブセラピーは、クライアントが変化への抵抗を感じないように、
希望や可能性を強調することを重視しています。
問題を外在化することで、クライアントが問題に押しつぶされることなく、
変化への希望を持つことができるよう支援しています。
また、クライアントの強みや能力に着目し、変化を起こす力を
引き出すことで、エンパワメントを促進しています。
6.まとめ
この理論は心理学においては、ナラティブ・セラピーだけではなく、家族療法や
ソリューション・フォーカスト。セラピーなど様々な療法にも影響を与えています。
また心理学だけでなく、教育学、社会学、文化研究、組織論など
幅広い分野に影響を与えています。
特に、固定的な枠組みを見直し、対話や協働を通じて新しい現実を
構築する方法論に貢献しています。
ナラティブ・セラピーにおいては、社会構造主義の限界を認識しつつ、
活用できる点を取り入れながら限界を克服するための独自の工夫を
加えることで、クライアントのエンパワメントとwell-beingを促進することを
目指しています。
7.更に探求するための文献
ナラティブ・セラピーと社会構造主義について
「ナラティヴ・セラピー 社会構造主義の実践」
遠見書房 マイケル・ホワイト、デヴィッド・エプストン他(著)野口裕二、野村直樹(訳)
ナラティブセラピーの創始者であるホワイトとエプストンによる著書。
社会構成主義の視点からナラティブセラピーの理論と実践を解説しています。
「ナラティヴ実践地図」
金剛出版 マイケル・ホワイト(著) 小森康永、奥野光(訳)
ナラティブセラピーの実践的なガイドブック。具体的な技法や事例を豊富に紹介しています。
「外在化」「再著述」「リ・メンバリング」「定義的祝祭」「ユニークな結果」「足場作り」という
ナラティヴセラピーの6つの主要な技法を、臨床場面でどのように用いるのかについて、
解説されています。
「ナラティヴ・セラピー入門:カウンセリングを実践するすべての人へ(社会構成主義の地平)」
北大路書房 マーティン・ペイン(著)横山克貴、バーナード紫、国重浩一(訳)
ナラティブセラピーの基礎を分かりやすく解説した入門書。
社会構成主義との関連性についても触れられています。
社会構造主義について
「現実の社会的構成―知識社会学論考」
新曜社 ピーター・L・バーガー、トーマス・ルックマン(著) 山口節郎(訳)
社会構成主義の古典的名著。社会がどのようにして知識を構築し、
それがどのようにして客観的な現実として認識されるようになるのかを解説しています。
「あなたへの社会構成主義」
ナカニシヤ出版 ケネス・J・ガーゲン(著)東村知子(訳)
社会構成主義の主要な論点を分かりやすく解説した入門書。
心理学における社会構成主義の応用についても触れられています。