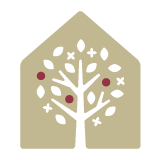ナラティブセラピーとは
世界中で、多くの人が抱える心の問題。 その解決に、『物語』が役立つとしたら?
人生は、一冊の物語。
そして、ナラティブセラピーは、あなたの人生という物語を、
より良い方向へと導くための羅針盤です。
うつ病や不安症、トラウマなど、様々な心の問題を抱える人々が、
ナラティブ・セラピーを通して、自分らしい生き方を取り戻しています。
ここでご紹介するナラティブ・セラピーの情報があなたの探求のお役に立てるとうれしいです。
1. ナラティブ・セラピー歴史と背景
ナラティブ・セラピーは、1980年代から1990年代にかけて、
マイケル・ホワイトとデヴィッド・エプストンによって提唱された
心理療法です。
彼らは従来の心理療法の問題解決アプローチに代わり、
「人々の物語」を中心とした新しい視点を提供しました。
このセラピーは、20世紀の社会構成主義やポスト構造主義哲学、
特にフーコーの権力と知識の関係性の考え方や、言説といった
考え方の影響を受けています。
また、文化や社会的文脈の中で自己と問題を
再考することを重要視しています。
2. ナラティブ・セラピーの理論背景
ナラティブ・セラピーの基盤は、次のような理論に支えられています。
社会構成主義
社会構成主義は、「現実」は客観的なものではなく、人々の間の言語や
社会的相互作用を通じて構築されると考えます。
ナラティブセラピーでは、問題や自己概念を「ひとつの物語」として捉え、
これを再構築できるものとみなします。
ポスト構造主義
特にフーコーの思想に基づき、
「問題は権力や社会的な語りによって形作られる」という視点を採用します。
フーコーの思想の中核には言説(ディスコース)というものがあります。
言説を短く表現をすると
『特定の時代や社会において、あるテーマについて語ることのできる言葉、概念、表現の総体』です。
つまり
『あるテーマについて、その時代や社会では、どのように捉え説明し表現し語っているか』ということです。
例えば、精神疾患について考えたとき
現代では、ストレス、認知や、脳の機能障害、遺伝的要因などの
生物医学的な要因から語られることが多いでしょう。
しかし、かつて中世ヨーロッパでは、悪魔憑きや神の罰といった
宗教的な言説で語られていました。
『あるテーマについてどのように話されるかは、時代や社会によって変わってくる』
つまり、時代や社会が変われば、人々の考え方や価値観、知識も変わるのです。
この考えに影響を受け、ナラティブ・セラピーでは、
問題の本質はクライアントの中にあるのではなく
問題は、自分の外、社会にある物語の中にあると
捉え直し、外在化という方法を生み出しました。
そして個人が持つ問題を再解釈し、
新たな可能性を発見していきます。
言語の役割
ナラティブセラピーでは、言葉が自己理解や現実構築の主要な手段とされ、
セラピーを通じて新しい物語を作るための対話が重視されます。
3. 主要な手法
ナラティブセラピーは非指示的なアプローチを採り、
主に次のような手法を用います。
外在化(Externalization)
問題を個人から分離し、客観化することで、クライアントが
問題に支配されるのではなく、問題に対処する力を得られるようにします。
例えば、
「私はうつ病です」という表現の代わりに
「うつ病が私の生活に影を落としています」と表現することで、
クライアントはうつ病と戦う主体として位置づけられます。
「私は怒りっぽい人間です」と表現する代わりに
「生活の中で怒りがこみあげてくることがある」というように
表現を変えることで、問題に対処しやすくなります。
ユニークな結果(Unique Outcomes)
問題に支配されていない例外的な瞬間を探し出し、
それを強調することで、クライアントの力を引き出し、
新たな可能性を創造します。
例えば、クライアントが「いつも不安に襲われる」と訴えている場合でも、
「先日、プレゼンテーションで成功したときには、不安を感じなかった」
という経験を引き出すことで、クライアントの自信と能力を再認識させます。
再著述(Re-authoring)
クライアントが自らの物語を振り返り、新しい視点で捉えなおし、
問題を強く感じていた記憶から解放されることを支援します。
過去の経験を再解釈することで、自分自身のポジティブな物語を創りなおし、
未来への希望を見出すことができます。
リ・メンバリング(Re-membering)
忘れられていた、あるいは抑圧されていた記憶や経験を思い出し語りなおすことで、
クライアントのアイデンティティを再構築します。
思い出すことで、自分のリソースを再び仲間に迎え入れるのです。
社会的文化的影響の認識
問題を個人の失敗ではなく、社会や文化によって作られた制約や
期待として再考するアプローチです。
証人
セラピーの過程で、クライアントの物語を聴き、その変化を認め、
支持する人たち(家族、友人など)を招き入れることで、
クライアントの新しい物語を社会的に強化します。
4. 他のセラピーへの影響
ナラティブセラピーは心理療法の分野で広範に影響を与えてきました。
短期療法やソリューション・フォーカスト・アプローチ
問題よりも解決に焦点を当てるこれらの手法と共鳴する点が多く、
物語の再構築を通じた短期的な変化を促します。
家族療法
家族全体の物語やコミュニケーションパターンを変化させることは、
家族療法にも影響を与えました。
トラウマ療法
トラウマを過去の固定された物語ではなく、克服可能な物語として
再解釈する方法論が多くのトラウマ治療法で採用されています。
ポストモダンアプローチ
他のポストモダン的な心理療法の進展にも貢献し、
特に個人のアイデンティティや権力構造に対する認識の変化に寄与しました。
5. ナラティブセラピーの強みと課題
強み
クライアント中心で協働的なアプローチを重視します。
言語の力や社会文化的背景を考慮した柔軟な方法論を提供します。
問題ではなく希望に焦点を当てるため、ポジティブな変化が生まれやすい。
課題
社会文化的背景や言語への理解が深くない場合、効果が限定的になる可能性があります。
非構造的な性質から、標準化や研究による効果検証が他の手法に比べて難しいようです。
6. まとめ
ナラティブセラピーは、従来の心理療法が抱える「治療者の指示的アプローチ」や
「固定された自己認識」への挑戦として生まれ、言語や物語を通じた柔軟で
希望に満ちたアプローチを提供しています。
心理療法分野におけるその革新性と影響力は現在も続いており、
多様なクライアントと社会文化的背景に適応できる可能性を秘めています。
参考
マイケル・ホワイト、デヴィッド・エプストン他著『ナラティブ・セラピー ー社会構造主義の実践』 遠見書房