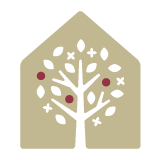ナラティブ・セラピーとミルトン・エリクソンの共通点
ナラティブ・セラピー創始者の一人マイケル・ホワイトとミルトン・エリクソンは、両者とも心理学や心理療法の分野において非常に影響力のある人物です。
二人が直接交流したことがあるかどうかは不明ですが、彼らのアプローチには異なる側面がある一方で、彼らの思想や方法論には重なる部分もあります。
そこで、ここでは、エリクソンとナラティブ・セラピーの共通点に注目してまとめました。
1.ナラティブ・セラピーとは
ナラティブセラピーは、人々が自分の人生を「物語」として捉えることで、自らの問題や経験に新たな視点を持ち、前向きな変化を促す心理療法です。
問題を個人そのものではなく、物語の一部とみなし、それを「外在化」して扱うことで、新しい物語を再構築する可能性を探ります。
セラピストは指示的ではなく、クライアントとの対話を通じて、彼らが持つリソースや可能性を引き出し、自ら変化する力を見つける手助けをします。
ナラティブ・セラピーでは、クライアントが自分の「物語」を振り返り、問題が自己の物語にどのように組み込まれたかを再解釈することによって、解放感と新しい希望を得ることを促進します。
「その人が問題なのではなく、問題が問題なのだ」
2.ナラティブセラピーにおける理論背景
マイケル・ホワイトとデヴィッド・エプストンによって提唱されたナラティブセラピーは、社会構成主義とポストモダニズムの影響を受けています。
社会構成主義の理論は、「現実」は客観的に存在するのではなく、社会的および言語的な相互作用を通じて構築されるとします。
ポストモダニズムは、単一の客観的な真実は存在せず、人それぞれが独自の解釈を持つという考え方を重視します。
これらの影響は、ナラティブ・セラピーがクライアントの物語を尊重し、多様な解釈を許容することに繋がっています。
初期のころは、グレゴリー・ベイトソンの影響も受けていたようです。
3. ミルトン・エリクソンについて
ミルトン・エリクソンは、催眠療法を含む多くの心理療法技法を革新した人物として知られています。
彼のアプローチは、特にクライアントとの協働的な関係と、言語や暗示を使って無意識の力を引き出す手法が特徴的です。
エリクソンは、問題解決をクライアント自身が自然に導けるように促すことを重視しており、この考えは後の多くの療法に影響を与えました。
4. 共通する点
言語の重要性(物語やメタファーの利用)
エリクソンもナラティブ・セラピーも、言葉や対話の力を強調し、またクライアントに新たな視点を提供するために物語や比喩を多用しました。
エリクソンは暗示や語りかけを用いて無意識的なリソースを引き出すことを重視し、ホワイトは物語を活用する手法を提案しました。
どちらも言語が治療過程で重要な役割を果たすという点で共通しています。
複数の解釈を許容
エリクソンは、クライアントの体験や症状を一つの固定された真実として扱わず、他の解釈を探索することを重視しました。
ナラティブ・セラピーも、物語の再解釈の仕方はセラピストから提供されるものというよりはクライアントの内側から喚起され、発見されることを重視しています。
クライアントの力を信じるアプローチ(リソース指向)
エリクソンは、クライアントが自身の問題解決能力を持っていると信じ、彼らが自らの無意識的リソースを見つけ出す手助けを行いました。
ナラティブ・セラピーも、クライアントが自分の物語を主導し、自己の力を再認識することを助ける方法を取りました。
双方とも、クライアントの内的リソースと力を引き出すことにフォーカスしています。
ナラティブセラピーでは「人は問題よりも大きい」という原則に基づき、クライアントを「問題を抱えた人」としてではなく、「変化を起こせる人」として捉え、クライアントをサポートします。
エリクソンも様々な場面で「人は変わることができる」ことを強調しています。両者とも、クライアントを「変化を起こせる人」と捉えています。
共創的な関係
エリクソンは治療者とクライアントが協働し、治療的な関係を築くことを大切にしました。
ホワイトも、ナラティブ・セラピーにおいて治療者とクライアントが協力することに重点を置いていました。
この共創的なアプローチは、両者の療法に共通しています。
間接的アプローチ
エリクソンの催眠療法は、直接的な指示を避け、クライアントが自ら変化する機会を提供する間接的アプローチを採用していました。
ナラティブ・セラピーも、アプローチは間接的であり、セラピストはクライアントの物語を「修正」しようとせず、クライアントが新しい物語を発見するための空間を提供します。
どちらも、問題を固定的な真実ではなく、再構築可能な物語の一部であると捉えます。
ユニークな物語の発掘
エリクソンは過去の経験や個々の体験の特異性、独自の視点に目を向け、そこに解決の糸口を見出しました。
一方で、ナラティブセラピーでは、クライアント自身が過去の物語から新たな意味を再解釈し、自己を肯定的に捉え直すことを重視します。
このように、両者とも「既存の枠を超えた視点」を促進するという点で重なります。
問題の外在化
「外在化」はナラティブ・セラピーの特徴の一つです。「外在化」とは、問題を人から分離し、客観的に扱うことで、クライアントが問題に支配されるのではなく、問題に対処できる存在として問題を扱うことです。
外在化もエリクソンの手法と共通するところです。
抵抗への対応
エリクソンはクライアントの抵抗を、変化への自然な反応と捉え、それを利用して治療を進めることを重視しました。
ナラティブセラピーも、クライアントの抵抗を否定せず、むしろそれを理解し、尊重することで、新たな物語を創り出すことを目指します。この点も共通点として挙げられます。
4.まとめ
マイケル・ホワイトとミルトン・エリクソンの間には直接的な師弟関係や明確な相互作用があるわけではありませんが、
彼らのアプローチには共通するテーマがあり、言語やクライアントの力を重視する点で一致しています。
それぞれが独自の方法論でありながらも、彼らの思想は、互いに補完しあう可能性を示しています。
参考書籍
マイケル・ホワイト、デヴィッド・エプストン他著『ナラティブ・セラピー ー社会構造主義の実践』 遠見書房
J.ヘイリー著 高石昇訳『戦略的心理療法 ミルトン・エリクソン心理療法エッセンス』 黎明書房