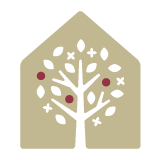このサイトの管理人です。このページはアフィリエイトプログラムを利用しています。
情報がお役に立てれば幸いです。
ポスト構造主義やジャック・デリタ、ミシェル・フーコー(Michel Foucault)の思想は、
現代思想や哲学を学ぶうえで重要な柱であり、ナラティブセラピーにもしばしば引用されます。
これらを理解することは、ナラティブ・セラピーの背景にある考えに触れることであり、
セラピーの仕組みを深く洞察する助けになります。それぞれを以下に説明します。
ポスト構造主義とは
ポスト構造主義は、20世紀半ばに登場した哲学的運動で、
特に構造主義への批判や展開として生まれました。
構造主義が「普遍的な構造や規則」を探るのに対し、
ポスト構造主義は「固定的な構造」や「客観的な真実」の
概念に疑問を投げかけ、より流動的で相対的な視点を提唱します。
構造主義とポスト構造主義の違い
構造主義(クロード・レヴィ=ストロースやロラン・バルトなど)
人間の文化や行動は、言語や社会の背後にある
普遍的な「構造」によって形成されると主張します。
ポスト構造主義(フーコーやジャック・デリダなど)
その「構造」が固定的ではなく、歴史や文化の中で
流動的に作られると考えます。
言語や意味は流動的で、真実は複数存在と考えます。
ポスト構造主義の基本的な概念
テキストとしての世界
あらゆる現実は「テキスト」のように解釈される対象とされ、
唯一の客観的な意味は存在しないと考えます。
意味の不安定性
言葉や概念は明確な意味を持たず、文脈や使用状況によって
解釈が異なります。これを「意味の多義性」と言います。
権力と知識の関係性
知識や真実は権力関係と結びついており、
「誰が真実を語るのか」によってその意味が構築されるとします。
主体の分散性
個人(主体)は固定された存在ではなく、社会や文化の
影響を受けて複数の役割やアイデンティティを持つとします。
【テキストとしての世界】について
テキストとしての世界、という考え方は、世界が現実そのものが
「テキスト」のように読み解くべき対象だという比喩的な意味をもっています。
「テキストしての世界」が意味すること
(1)意味は固定されない(意味の不安定性)
・どんなテキスト(文章や出来事)にも、唯一の客観的な意味や解釈はない。
・文脈や状況、観察者(読み手)の経験によって、テキストの解釈は無数に変わり得るということ。
例:歴史書
ある歴史的出来事について書かれた本は、著者の視点や時代背景によって意味が形成されます。
同じ出来事を他の時代や文化圏で語ると、まったく異なる解釈になるかもしれません。
(2)前後関係(文脈)が意味を決定する
・言葉や行動、出来事の意味は、それが置かれた「文脈(コンテクスト)」によって変化します。
・文脈とは、「そのテキストがどのような状況で存在しているか」「何と関連しているか」といった周囲の情報を指します。
例:単語「バンク」
英語の「bank」という単語は、文脈によって「銀行」「川岸」「傾き」のいずれかに解釈されます。
これがポスト構造主義的な意味での「テキストの解釈」につながる考え方です。
(3) 現実そのものが「テキスト」である
ポスト構造主義者(特にジャック・デリダ)は、現実そのものが「言語を通じて構築される」と主張します。
我々は世界を直接見るのではなく、「言葉」を通じてそれを理解します。
この「言葉」が現実を構築する手段であり、現実は一つのテキストとして機能します。
例:文化や規範
・「正しい/間違っている」という概念は普遍的ではなく、社会的なルール(つまり言葉)によって定められる。
・一つの行動が「正常」とされるか「異常」とされるかは、その社会で支配的な価値観(=ディスコース)が
どのように「意味付け」したかによる。 と考えられます。

「テキストとしての世界」とは、以下のように解釈できます。
・すべての現実や出来事、文化は「解釈されるべきもの」として存在している。
・その解釈は文脈や背景、社会的・歴史的条件によって決まる。
・唯一の客観的な意味や解釈は存在せず、意味は常に多義的で変化可能である。
この考え方を理解することで、物語や社会の中での自分自身や他者の位置付け、
また固定観念からの解放について、より深い洞察を得ることができるでしょう。
テキストとジャック・デリダの「脱構築(解体)」
ポスト構造主義の思想家ジャック・デリダが提唱した
「脱構築(deconstruction)」は、この「テキスト」の考え方を深化させました。
脱構築の考え方
言葉やテキストには、明示的な意味(書かれていること)と、
隠された暗黙の前提(言葉の背後にある意図や前提)が存在します。
デリダはテキストを「脱構築(解体)」し、その明確な意味の裏側に潜む
前提や矛盾を探ることを重視しました。
例:フェミニズム文学の分析
「男は力強い」「女は優しい」というテキストにおける明示的な意味だけでなく、
その背後にある性別に基づいた固定観念や権力構造を探る。
この分析によって、社会的に押し付けられた物語(ディスコース)を解体することができると考えます。
ジャック・デリダの「テキストの脱構築と再解釈」の
考え方が、ナラティブセラピーの中核である
「クライアントの問題を取り巻く物語(ナラティブ)の見直し」
というアプローチに直結しています。
脱構築がナラティブセラピーに与えた影響をいくつかのポイントに分けて詳しく説明します。
脱構築がナラティブセラピーに与えた影響
1. 問題の「物語化」と脱構築
ナラティブセラピーでは、人々が抱える問題を「問題としての物語」として捉えます。
この「問題としての物語」は、社会的な規範や文化的な語り(ディスコース)によって形成されると考えます。
デリダの脱構築は、これらの物語や規範が固定的なものではなく、再解釈や変化が可能であることを示唆します。
【デリダの影響】
問いかけによる脱構築
セラピストはクライアントが信じている物語の構造や前提を批判的に見直すことで、それを「脱構築」します。
新たな解釈の可能性
問題や自己像を支配する物語を分解し、新しい可能性を見出す支援を行います。
これにより、クライアントは自己の物語を再構築できるようになります。
2. テキストとしての人生
デリダは、すべての現実を「テキスト」として解釈可能であり、それ自体が主観的かつ多義的だとしました。
この考え方は、ナラティブセラピーが人生の出来事を「物語」として捉える基盤となっています。

クライアントが「自分は失敗者だ」という物語を抱えていたとします。
その物語を「どのように構築されたのか」という文脈(例えば、過去の経験や他者の期待)から振り返ると、新しい視点が生まれます。
例えば、「挑戦した証」や「努力を認識する経験」として再構築される可能性があります。
3. ディスコースの批判
デリダの脱構築は、社会的な「ディスコース(言語を通じて形作られた現実)」を批判的に見直す重要性を強調します。
ナラティブセラピーでは、クライアントが問題として認識している背景には、多くの場合、社会的な期待や固定観念が絡んでいると考えます。
デリダの影響:既成概念への挑戦
クライアントが抱える問題が「個人的失敗」として語られていても、それは社会や文化が押し付けた価値観や基準によって作り出されているかもしれません。
例:「痩せていないと価値がない」という規範を再評価することで、「健康的で自分らしい美しさ」に焦点を当てられるようにするなどができます。
4. 言語の不安定性と意味の多義性
デリダは、「言葉の意味は固定されず、文脈によって常に変化する」と考えました。
デリダはこれを差延(différance)と名づけました。
差延différanceはフランス語で
これは "différence"(差異)と "différer"(延期する)という二つの言葉を掛け合わせた造語です。
差異: 言葉の意味は、他の言葉との差異によって生み出される。
延期: 言葉の意味は、常に他の言葉へと送り続けられ、確定することがない。
つまり、「差延」とは、言葉の意味が、他の言葉との差異によって生み出されながらも、
常に他の言葉へと送り続けられ、確定的な意味を持たないという、動的なプロセスを指す概念なのです。
例えば、辞書で「机」という言葉の意味を調べたとします。
辞書には、「机」の説明として、
「板状の天板と脚からなる家具。物を書いたり置いたりするのに用いる。」といった記述があるでしょう。
しかし、この説明文で使われている「板状」「天板」「脚」「家具」「物」「書く」「置く」といった言葉も、
それぞれ他の言葉との関係性の中で意味が決まります。
さらに、これらの言葉を説明するために、また別の言葉が必要となり、その言葉もまた、
他の言葉によって説明される…というように、意味は際限なく他の言葉へと送り続けられ、
最終的な意味に到達することはありません。これが「差延」です。
ナラティブセラピーにおいて、クライアントが語る「問題」もまた、言葉によって構成された物語です。
そして、その物語は、クライアント自身の経験や、周囲の人々との関係性、社会的な文脈など、
様々な要素が絡み合って作られています。
デリダの「差延」の考え方は、クライアントが語る「問題」もまた、固定的なものではなく、
常に変化し続ける可能性を秘めていることを示唆しています。
これは、ナラティブセラピーが問題を言葉として定義することの流動性を強調する点と一致します。
セラピストは、クライアントの物語に耳を傾け、その中に含まれる様々な言葉や意味を
丁寧に探っていくことで、クライアント自身が新たな解釈や可能性を見出すことができるよう支援します。
言葉への疑問
クライアントが「私は無価値だ」と語った場合、その「無価値」という言葉が具体的に何を意味し、どの文脈でその解釈が生まれたのかを探ります。
これにより、「無価値」という自己評価が曖昧で主観的であることが示され、新しい意味や語りが生み出されます。
5. 新たな物語(オルタナティブナラティブ)の構築
デリダの「脱構築」は、「解体」が最終目的ではありません。
既存の意味や解釈を解体することによって、新しい可能性や多様な解釈を見出すことが目指されています。
同様に、ナラティブセラピーでは、クライアントが自己や人生について新しい物語を構築できるよう支援します。
例
元の物語:「私はいつも間違いばかりする。」
脱構築を経た新しい物語:「私は間違いから学び、成長するために努力している。」
6. デリダのナラティブセラピーへの実践的応用
デリダの影響は、ナラティブセラピーの「外在化」や「ユニークアウトカム」といった具体的な手法に反映されています。
(1) 外在化(Externalization)
問題を人間から切り離し、「あなた」ではなく「問題が問題である」と語る手法。
→ これは、デリダが「言葉や物語は現実を固定するものではない」と考えたことと一致します。
(2) ユニークアウトカム(Unique Outcomes)
支配的な物語とは異なる成功体験や小さな物語を発掘し、新しい物語の構築の基盤とする。
→ これは、「脱構築」によって既存の解釈を乗り越え、新しい視点を開くプロセスと対応します。
(3)リ・オーサリング(Re-Authoring)
問題で一杯になっている物語のディスコースを当然のこととして受け入れるのではなく、
批判的に吟味することを通して脱構築し、新たな物語(オルタナティブナラティブ)を
構築するまでの一連の流れを、リ・オーサリングと呼びます。
ここには、デリダの理論におけるテキストや差延の理論も背景にあります。
ミシェル・フーコーの思想
フーコーはポスト構造主義の中心的な思想家であり、特に権力と知識、主体性の関係をテーマに多くの洞察を残しました。
フーコーの理論の概要は以下です。
権力の分散性
ミシェル・フーコーの権力論における「分散性(diffusion)」とは、権力が特定の個人や機関(例えば、国家や王)に
集中しているものではなく、社会のあらゆる関係性やネットワークの中に浸透しているという考え方を指します。
・権力は関係性の中に存在する
フーコーにとって権力は「人々の相互作用の中で形成され、実行されるもの」です。
これは縦に構造化された「支配者―被支配者」のような一方的な力ではなく、相互作用的かつ流動的なものです。
・権力は分散している
権力は特定の個人や集団に集中するのではなく、社会全体に広がっていると考えます。
つまり、政治的・経済的機関だけでなく、家族、教育、職場など、どんな小さな社会集団の中にも権力構造が存在します。
・抵抗も権力の一部である
権力の分散性の核心の一つに「抵抗の可能性」があります。
権力は常に完全ではなく、必ずその中に「抵抗」が伴うという考えです。
権力は人々を抑圧するだけでなく、生産的な側面、可能性を生み出す力をも持つと考えます(例: 社会規範を作り、人々の行動を方向づける)。
知識と権力の相互関係
知識は権力によって形作られ、権力は知識を支えることで正当化されます。
フーコーは「知識」と「権力」は切り離せない関係にあると指摘しました。
知識は、権力を維持し強化するためのツールとなり、同時に権力によって生成されます。
この関係は、社会的に人々を「規範的」行動に導きます。
この概念を「知=権力(power/knowledge)」と呼んでいます。
例
医学や精神医学は、正常/異常、健康/病気といった枠組みを作り出し、それに基づいて患者が分類され、治療される。
この「知識の制度化」が医師や医療機関に権力を与える、と考えます。
ディスコース(言説)
ディスコースとは
「社会における知識、価値観、真実を作り出すコミュニケーションの枠組み」
「社会的現実を構成する一連の言語的習慣」を指します。
わかりやすく言い換えると、「ある言葉を、どのように解釈し意味づけているか」ということです。
ディスコースの特徴
・現実を構築する
私たちが物事をどのように「意味づけ」するかは、ディスコースに影響を受けています。
例えば、「成功」という概念がどのように定義されるかは、社会や文化によって異なります。
・排除と包括のメカニズム
あるディスコースが強化されると、その裏側にある他の可能性や視点は抑圧される場合があります。
これにより「支配的ディスコース」と「マイノリティ的ディスコース」が生まれます。
・時代や文脈による変化
ディスコースは固定的ではなく、常に変化しています。
過去には支配的だったものが、社会の変化により新たな視点へと置き換わることもあります。
例
「家族」という概念:ある時代には「夫、妻、子ども」で構成される家族像が一般的だったものが、
近年では多様な形態(シングルマザー、同性カップル、共同生活者など)が家族として認められるようになってきています。
規律と監視社会
フーコーは近代社会が「規律」と「監視」によって人々の行動を管理する仕組みを持つと指摘しました。
「パノプティコン」という概念を通じて、監視されている可能性そのものが自己規律を促進することを説明しました。
(例: カメラがなくても監視カメラを意識すると行動が変わる)
歴史的問い直し
フーコーは、近代的な知識や制度がどのようにして歴史的に形作られてきたかを分析しました。
例として、狂気、病気、犯罪などの概念の変遷を考察しています。
フーコーの思想のナラティブセラピーへの影響
フーコーの思想は、ナラティブセラピーの基本的なアプローチに大きな影響を与えています。
言説の解体
ナラティブセラピーでは、クライアントが自分に押し付けられた社会的・文化的な物語(ディスコース)を見直し、自分の言葉で新しい物語を作る支援を行います。
支配的ディスコースは、人々に特定の価値観や行動様式を押し付ける力を持っています。
ナラティブセラピーでは、クライアントがこうした支配的なディスコースによって形成された「支配的物語」を無意識に受け入れている場合が多いと考えます。
セラピーのアプローチ
セラピストは、クライアントが「支配的物語」をどのように内面化し、それが現在の問題に影響を与えているのかを探ります。

例えば、クライアントが「私はダメな親だ」という信念を持っている場合、その背後には「良い親はこうあるべきだ」という支配的なディスコースがあるかもしれない、と可能性を考えることができます。
権力との関係
問題が個人の中に内在しているのではなく、社会的・文化的な権力関係によって作られたとみなすアプローチはフーコーの「知=権力」の視点と一致しています。
外在化の手法
ナラティブセラピーでは問題をクライアント自身から「切り離す」外在化の手法を用います。
クライアントが抱える問題が単に「個人的な失敗」や「性格の欠陥」ではなく、社会的なディスコースによって形成されたと理解することで自己批判を軽減し、新しい視点を得られるようになります。
問題をクライアントの一部ではなく外部に置く考え方は、フーコーの「個人が権力によって規範化される」という洞察と関連しています。
オルタナティブ・ストーリー(Alternative Story)の創造
ナラティブセラピーでは、支配的ディスコースに挑戦し、クライアント自身が選び取る「オルタナティブ・ストーリー」を構築します。
ディスコースの再解釈: 社会の中で抑圧されたり見過ごされた「小さな物語」や「新しい声」をクライアント自身が発見し、それを強化するプロセスがセラピーの一部です。

例えば「職場での評価ばかり気にする」という支配的物語を持つクライアントが、自分の人生における他の価値観(例えば、家族や趣味、自己成長など)を再評価し、新たな意味を見いだすことができます。
フーコーの理論が応用される場面例
「私は無能だ」と感じているクライアント
フーコー的視点では、「無能」という感覚は自己の中に本質的に存在するのではなく、成功や能力に対する社会的な基準や言説の影響によるものだと考えます。
セラピストは、クライアントがその「無能」という物語の起源や影響を探り、それにとらわれない新しい意味を構築できるよう支援します。
デリダとフーコーの共通点と相違点
フーコーとデリダはどちらもポスト構造主義に属していますが、それぞれ独自の視点を持っていました。
そして、ナラティブセラピーとの関連でいうと、両者とも「主体の脱構築」を主張している点は共通しています。
一方で、、フーコーは権力関係からの解放を重視するのに対し、デリダは言語による固定化からの解放を重視しています。
まとめ
ジャック・デリダの「脱構築」、ミシェル・フーコーの「権力の分散性」や「言説(ディスコース)」に
特徴づけられるポスト構造主義の理論は、ナラティブセラピーに次のような重要な影響を与えています。
「問題の物語」の脱構築
ポスト構造主義では、言語の不安定性や意味の多義性が強調されます。
この視点は、クライアントが抱える「問題としての物語」を分析し、既存の解釈の枠組みや支配的なディスコースを問い直すプロセスに直結します。
ナラティブセラピーの「脱構築的会話」を通じて、問題の物語を見直し、新しい意味を構築する(リ・オーソリンング)実践につながっています。
ディスコースの影響を明らかにする
クライアントの問題を個人的な失敗や内面的な欠陥ではなく、社会的・文化的なディスコースの結果として捉える視点を提供します。
これにより、クライアントは自身が抱える問題が、特定の社会的なルールや価値観(例:性別、家族観、経済的な成功観など)によって形成されている可能性に気づくことができます。
問題の外在化
ミシェル・フーコーの理論から着想を得た「権力と主体性」の概念は、ナラティブセラピーにおける「外在化」の技法にも影響を与えています。
問題をクライアント自身から切り離し、別個の存在として捉えることで、クライアントが問題に取り組む力を引き出す(エンパワーメント)プロセスを助けます。
セラピストとクライアントの関係性
ポスト構造主義の批判的視点は、セラピストが権威的な「専門家」としてではなく、クライアントと対等な関係で協働する姿勢を促します。
これにより、クライアントの物語が尊重され、セラピーのプロセスで主体性が強調されます。
オルタナティブストーリーの生成
クライアントのこれまでの「問題の物語」から新しい解釈や可能性のある物語へと移行するプロセスを支援します。
この「オルタナティブストーリー」の生成は、ポスト構造主義の視点に基づいて、複数の可能性を認めるアプローチの一部です。
まとめのまとめ
ポスト構造主義は、ナラティブセラピーにおける「物語の脱構築」と「再構築」という基盤的な概念に深い影響を与え、
クライアントの問題を社会的・文化的コンテキストの中で再評価することを可能にしています。このアプローチにより、
クライアントは自身の物語を主体的に再構築し、人生に新たな意味や方向性を見出すことができます。
さらに探求するための文献
「ナラティブ・セラピー・クラッシクス‐脱構築とセラピー」金剛出版 マイケル・ホワイト(著)小森康永(訳)
ナラティブ・セラピーの思想と実践について、創始者マイケル・ホワイトが遺したテクスト/インタビューより紐解く一冊です。
「知の考古学」河出文庫 ミシェル・フーコー(著)慎改康之(訳)
フーコーの最も重要とされる著作の新訳です。
「監獄の誕生〈新装版〉:監視と処罰」新潮社 ミシェル・フーコー(著)田村 俶(訳)
「デリダ 脱構築と正義(講談社学術文庫2296)」高橋哲哉(著)
脱構築について応用できるよう分かりやすく記載されていると評判の一冊です。ジャック・デリダを理解するには必須の一冊という評価もあります。