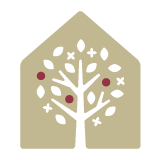ミルトン・エリクソンにも影響を与えたダブル・バインド理論
グレゴリー・ベイトソンのダブル・バインド理論は、コミュニケーションにおける矛盾したメッセージが、受け手に心理的な葛藤を引き起こすことを説明する理論です。
ダブル・バインドの条件
1. 重要な関係性: 受け手にとって、メッセージ発信者は非常に重要な人物である(例:親子、上司と部下など)。
2. 矛盾したメッセージ: 発信者は、言葉と非言語的コミュニケーション(表情、態度など)で矛盾したメッセージを伝える。
または、二つの相反する命令を与える。
3. 回避不能: 受け手は、その状況から逃れることができず、矛盾したメッセージに応答せざるを得ない。
1.の重要な関係性については、相補性の原則との関連があります。相補性の原則は後述します。
ダブル・バインドの具体例
●母親が子供に「こっちにおいで」と言いながら、顔をしかめて腕を組んでいる。
子供は、母親の言葉に従いたい気持ちと、拒否されているような気持ちの間で葛藤し、どうすれば良いか分からなくなる。
●上司が部下に「自分の意見を言え」と言いながら、部下が意見を言うと「生意気だ」と叱責する。
部下は、意見を言うべきか、それとも黙っているべきか、板挟みになる。
ダブル・バインドと精神病理
ベイトソンは、統合失調症などの精神病理の発症に、ダブル・バインドが深く関わっていると考えました。
繰り返しダブル・バインドにさらされることで、受け手は現実を正しく認識することが困難になり、思考や行動に混乱が生じるとされています。
ダブル・バインドと統合失調症の関連性に関する現代の視点について詳しくは後述します。
ダブル・バインドが統合失調症の原因なのではなく、むしろ結果なのではと考えられています。
フィードバックとの関連
ダブル・バインドは、コミュニケーションにおけるフィードバックの歪みと捉えることができます。
健全なコミュニケーションでは、発信者と受け手の間でフィードバックが適切に行われ、相互理解が深まります。
ダブル・バインドでは、矛盾したメッセージによってフィードバックが阻害され、受け手は発信者の意図を正確に理解することができません。
受け手は、混乱したフィードバックに基づいて行動するため、発信者の期待に応えることができず、さらに矛盾したメッセージを受け取ることになります。
この悪循環が繰り返されることで、コミュニケーションは破綻し、受け手の心理的な問題は深刻化していきます。
ダブル・バインドと相補性について
まず、それぞれの概念を確認します。
【ダブル・バインド】
矛盾したメッセージによって、受け手が心理的な葛藤に陥るコミュニケーションパターン。
【相補性の原理】
コミュニケーションにおいて、相手と異なる立場や役割をとることで、関係性が安定するという考え方。
例えば、
上司と部下、教師と生徒、親と子など、それぞれの役割が異なることで関係性が成り立っています。
一見すると、ダブル・バインドと相補性の原理は相反する概念のように思えるかもしれません。
しかし、ベイトソンは、ダブル・バインドは相補的な関係性の中でこそ生じやすいと指摘しています。
具体的に言うと、相補的な関係性においては、一方の立場が強くなりすぎると、もう一方を支配し、ダブル・バインドのような状況を作り出す可能性があります。
例えば、親子の関係において、親が常に権威的な態度で接し、子供に自分の意見を押し付ける場合、子供は親の顔色を伺い、自分の気持ちを抑圧するようになります。
このような状況下では、親が「自分の意見を言いなさい」と言っても、子供は本音を言えず、言ったとしても親の期待に応えられないため、叱責されるかもしれません。これは、まさにダブル・バインドの一例です。
つまり、相補性の原理は、関係性を安定させるための基本的な原則ですが、そのバランスが崩れると、ダブル・バインドのような相手を追い詰めるようなコミュニケーションパターンを生み出す可能性があると言えるでしょう。
さらに深く考えてみると
ベイトソンは、健全なコミュニケーションには「対称性」と「相補性」のバランスが重要だと考えていました。
対称性:
コミュニケーションにおいて、相手と同じような立場や役割をとることで、互いに理解し合うことを目指す。
相補性:
コミュニケーションにおいて、相手と異なる立場や役割をとることで、関係性を安定させる。
対称性と相補性のバランスがとれている状態では、互いに尊重し合い、自由な意見交換が可能です。
しかし、どちらか一方に偏ると、コミュニケーションが歪み、問題が生じやすくなります。
ダブル・バインドは、相補性が過度に強調され、対称性が失われた結果と言えるかもしれません。
ダブル・バインドと相補性のまとめ
ダブル・バインドと相補性の原理は、一見すると異なる概念ですが、深く関連しています。
相補的な関係性において、バランスが崩れるとダブル・バインドが生じやすくなることを理解し、対称性と相補性のバランスを意識することが、健全なコミュニケーションのために重要です。
ダブル・バインドの克服
ダブル・バインドを克服するためには、
・矛盾したメッセージに気づく
・状況から一時的に離れる
・信頼できる人に相談する
・メタコミュニケーション(コミュニケーションについてコミュニケーションをとること)を通して、問題を明確化する
などの方法が考えられます。
現代社会におけるダブル・バインド
現代社会では、情報過多や複雑な人間関係の中で、ダブル・バインドに遭遇する機会が増えています。SNSなどでのコミュニケーションにおいても、ダブル・バインドが生じることがあります。
ダブル・バインド理論は、コミュニケーションの複雑さを理解し、より良い人間関係を築く上で重要な示唆を与えてくれます。
より深く理解するために、以下の資料も参考になるかと思います。
参考書籍
『精神の生態学』 グレゴリー・ベイトソン著 佐藤良明訳 思索社1986年 は絶版になっているようなので以下があります。
『精神の生態学へ』(上)(中)(下) グレゴリー・ベイトソン著 佐藤良明訳 岩波文庫2023年
『ダブルバインド―自己の病理への理論』 グレゴリー・ベイトソン他著
統合失調症とダブル・バインドの関連 現代の視点
初期のダブル・バインド理論
ベイトソンは、統合失調症の発症に、家族内におけるダブル・バインドが主要な役割を果たすと考えていました。
特に、母親と子の間のコミュニケーションに注目し、母親の矛盾したメッセージが子供の精神に混乱をもたらし、統合失調症を引き起こすと主張しました。
現代の視点
ダブル・バインドの限定的な役割: 現代の研究では、ダブル・バインドが統合失調症の直接的な原因となるという考えは支持されていません。統合失調症は、遺伝的要因、神経生物学的要因、環境要因など、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。また、近年では、ダブル・バインドは統合失調症の原因ではなく、むしろ結果として生じるという考え方が有力になっています。
その中で、家族とのコミュニケーションは、統合失調症の発症そのものよりも、むしろ経過に大きな影響を与えるという視点が重視されるようになっています。
統合失調症の患者は、思考、感情、行動に困難を抱えているため、周囲の人とのコミュニケーションがうまくいかないことが多く、誤解や葛藤が生じやすくなります。
また、家族は、患者の症状に戸惑い、どのように接すれば良いか分からず、不安やストレスを感じることがあります。
こうした状況下では、家族のコミュニケーションがぎくしゃくし、意図せずダブル・バインドのような状況を作り出してしまう可能性があります。
つまり、家族が意図的にダブル・バインドを引き起こしているのではなく、患者の症状や家族のストレスが、結果としてダブル・バインド的なコミュニケーションパターンを生み出してしまうというわけです。
【具体例】
統合失調症の患者が、妄想や幻覚のために混乱した言動をとる。
家族は、患者の言動を理解できず、不安や恐怖を感じ、戸惑った態度をとる。
患者は、家族の態度から拒絶されていると感じ、さらに混乱し、症状が悪化する。
家族は、患者の悪化する症状にさらに戸惑い、コミュニケーションがうまくいかなくなる。
このように、悪循環に陥ることで、ダブル・バインドが生じやすくなります。
ダブル・バインドは、統合失調症の原因ではなく、むしろ結果だ、という考えは統合失調症の方のご家族にとっては大きな救いになることです。
そして、その中で、家族とのコミュニケーションは、統合失調症の発症そのものよりも、むしろ経過に大きな影響を与えるという視点が重視されるようになっています。
コミュニケーションの重要性: 家族や周囲の人々とのコミュニケーションが、統合失調症の経過に大きな影響を与えることは、多くの研究で示されています。
expressed emotion (EE): 感情表出。家族が高EE (批判的、敵対的、過度に介入的) であると、患者の再発リスクが高まることが知られています。これは、ダブル・バインドとまでは言えないまでも、患者にとってストレスとなるコミュニケーションパターンと言えるでしょう。
コミュニケーション療法: 統合失調症の治療において、家族療法や認知行動療法など、コミュニケーションに焦点を当てた心理療法が有効であることが示されています。これらの療法は、患者と家族がより良いコミュニケーションを学び、相互理解を深めることで、症状の改善や再発予防を目指します。