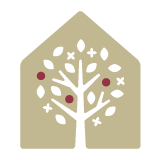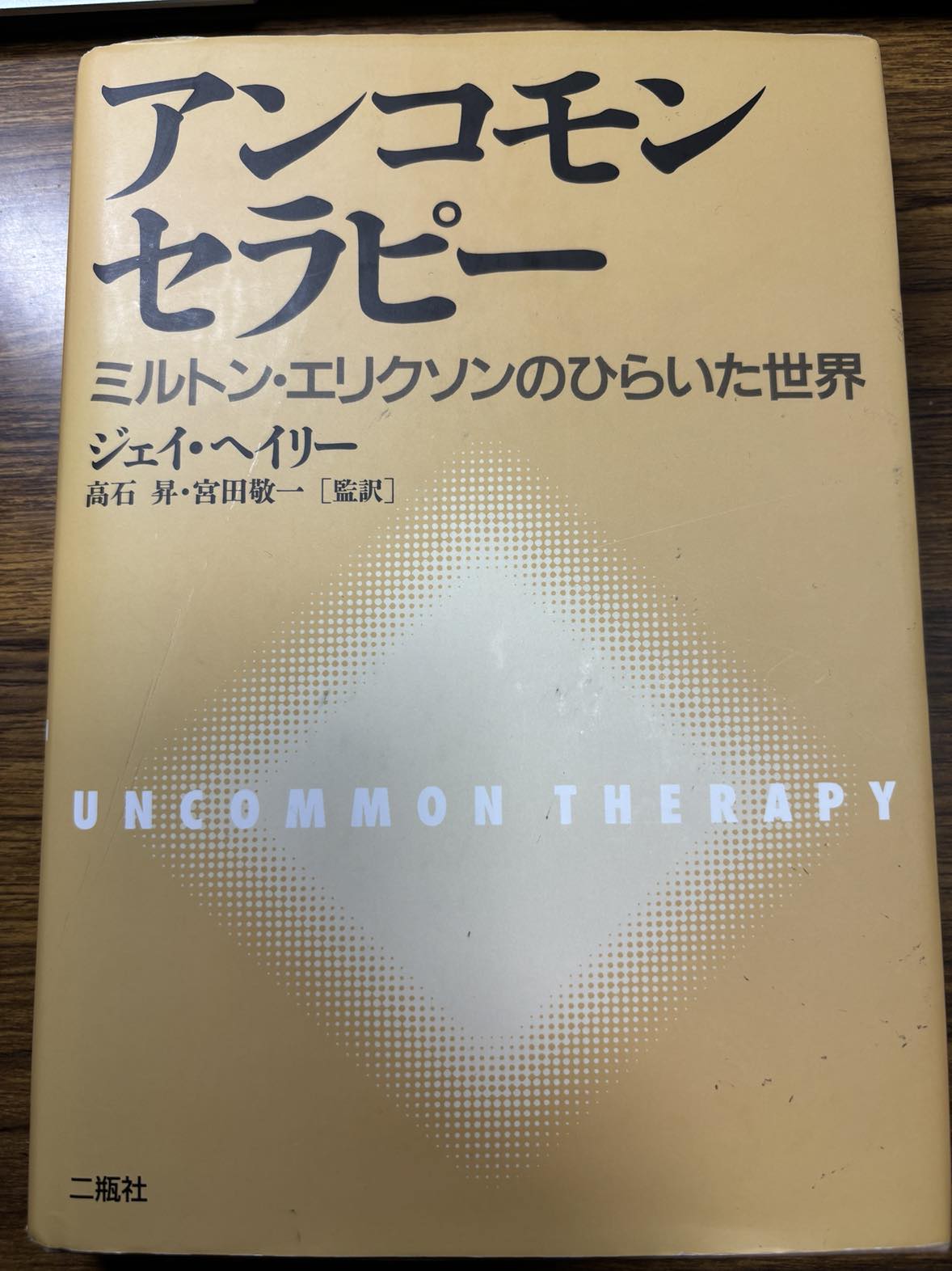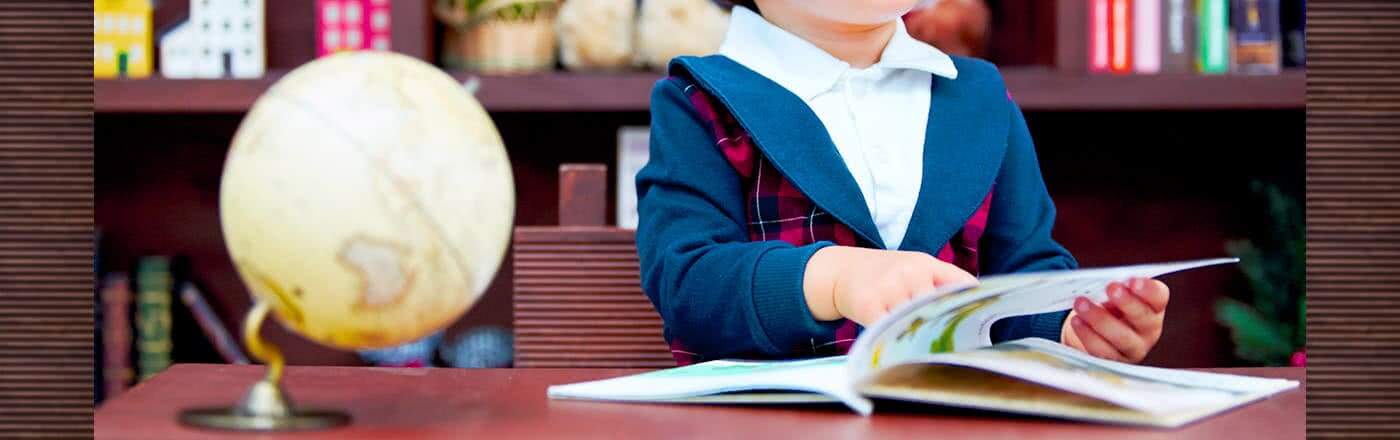
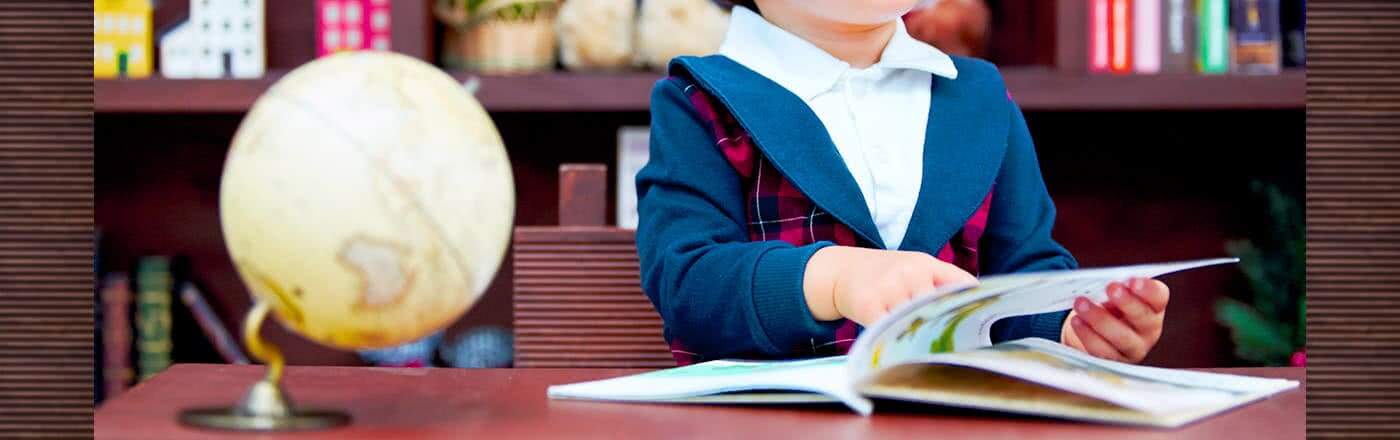
『アンコモン・セラピー』(原題: Uncommon Therapy)の概要
ミルトン・エリクソンの治療技法や考え方を紹介した書籍です。この本は、精神科医のジェイ・ヘイリー(Jay Haley)によって執筆され、エリクソンのユニークな心理療法のアプローチに焦点を当てています。
本書
『アンコモン・セラピー』は、ミルトン・エリクソンの治療法が当時、従来のセラピーで通常行われていたことと異なっていたことから、「通常とは異なる」という意味でタイトルがつけられました。
ミルトン・エリクソンは状況に応じた柔軟なアプローチを行い、 彼の技法には、催眠療法や暗示、逆説的介入などが含まれ、クライアントの無意識を活用することで、治療的な変化を受け止めることが描かれています。
催眠療法
エリクソンは催眠療法を革新的に発展させました。 彼は、無意識が個人の変化と成長を促進できる強力な力であると信じました。つまり無意識を肯定的な力を持つものだと捉え、それは、1940年代当時に精神医学界で主流だった精神分析的な考え方とは異なるものでした。そして暗示や比喩を用いてクライアントの無意識にアプローチする手法をとったのです。
逆説的なアプローチ
ミルトン・エリクソンは、クライアントの抱える症状や問題に対して、驚くべき逆説的な指示を与えることで知られています。彼は、クライアントが自らの症状をコントロールできることに気づかせる天才でした。
例えば、不安に苦しむクライアントには「もっと不安になってみてください」と、睡眠障害に悩むクライアントには「眠らないでいよう」と指示するのです。一見すると矛盾しているように思えるこれらの指示は、クライアントの無意識に働きかけ、問題に対する新たな視点と対処法を与えます。
「症状にこだわってみる」ように指示することで、かえって問題が軽くなるといった不思議な効果も、エリクソンの逆説的アプローチの特徴です。彼は、クライアントの苦労や葛藤に寄り添いながらも、彼ら自身の力で解決への道を見つけ出すことができるよう、巧みに逆説的な手法を活用しました。
エリクソンは、人間の無意識に眠る創造性と柔軟性を最大限に引き出し、クライアントを自由へと導いたのです。エリクソンはまるで魔法使いのように、クライアントの無意識に働きかけ、問題に対する新たな視点と対処法を与えるのです。
例えば、不安に押しつぶされそうなクライアントに、エリクソンは優しく語りかけます。「もっと不安になってみてください」。穏やかな口調と温かい眼差しは、クライアントの心を解きほぐし、指示の意図を深く理解させます。
1. 泥棒に悩まされる女性への指示
ある女性が、自宅に繰り返し泥棒が入ることに悩んでエリクソンのもとを訪れました。エリクソンは、彼女に驚くべき指示を与えます。「次に泥棒が入ったら、協力してあげてください。そして、盗みたいものを全部盗ませるんです」。女性は戸惑いながらも、エリクソンの真剣な表情からエリクソンの指示に従いました。すると、不思議なことに泥棒は二度と現れなくなったのです。
このエピソードは、エリクソンの逆説的アプローチがいかに効果的であるかを示す好例です。泥棒に協力するという行為は、女性の恐怖心や抵抗感を打ち破り、状況をコントロールできる感覚を与えました。
2. 引っ込み思案の少年への指示
引っ込み思案で友達ができない少年に対して、エリクソンは「一週間、誰とも口をきかないように」と指示しました。少年は、この指示にはじめは困惑しましたが、次第に自分自身と向き合う時間が増え、内省を深めていきました。エリクソンは少年に静寂の中で自分自身と向き合う時間を与えたのです。そして、一週間後、少年は自分から周りの人に話しかけるようになり、新たな友人関係を築くことができたのです。
このエピソードは、エリクソンの逆説的アプローチが、クライアントの隠れた能力や可能性を引き出す力を持つことを示しています。
3. 食事に偏りのある少女への指示
野菜嫌いで、偏食の激しい少女のケースでは、エリクソンは「絶対に野菜を食べてはいけない」と指示しました。少女は、この指示に喜び、他の食べ物を積極的に食べるようになりました。すると、しばらくして、禁止されていた野菜への興味が湧き上がり、自ら進んで食べるようになったのです。
このエピソードは、エリクソンの逆説的アプローチが、クライアントの抵抗感を逆手に取り、行動変容を促す効果を持つことを示しています。
これらのエピソードは、エリクソンの逆説的アプローチが、クライアントの隠れた能力や可能性を引き出す力を持つことを示しています。彼は、クライアントの苦労や葛藤に寄り添いながらも、彼ら自身の力で解決への道を見つけ出すことができるよう、巧みに逆説的な手法を活用したのです。
個別アプローチ
エリクソンは、とりあえずのクライアントが持つ問題や背景に応じて、治療法を柔軟に適用しました。ここでいう“とりあえず”というのは、クライアントの表に現れた、認識できる問題という意味であり、その奥にある真の問題があることを含意しています。
エリクソンの治療は、常にクライアントの個性や状況に応じてアプローチを変える「個別的」なものでした。彼は固定化された治療法を持たず、クライアントの背景、価値観、環境などを考慮し、その場で最も効果的だと感じた方法を柔軟に適用しました。クライアントごとに異なる問題解決方法を見つけ出し、彼らの自然な回復力を引き出すことを重視していました。彼のアプローチは標準的なマニュアルに沿ったものではなく、個別のケースに最適な対応を考えるものです。この個別アプローチがミルトン・エリクソンを難解だと思わせる理由の一つでもあり、多くの支援者が強烈な興味を抱き探求を続ける理由の一つでもありそうです。
家族療法との関係
エリクソンは家族療法にも大きな影響を与えました。 エリクソンはクライアント個人に焦点を当てながらも、家族というシステムの中で家族から働きかけることにより個人の問題を解決しようと試みました。
個人だけでなく、その人を取り巻く家族全体のシステムにも働きかける点で、家族療法に重要な影響を与えました。彼は、クライアントの行動や問題が家族の力学と密接に関連していると考え、家族全体を治療の一部として扱いました。エリクソンの治療は、家族のコミュニケーションや行動パターンを変化させることで、個々の問題を解決する手法を取ることがありました。
人間の変化の可能性
『アンコモンセラピー』では、エリクソンの「人間の変化の可能性」への信念や、独自の治療技法が紹介されており、エリクソンが催眠療法や短期療法に与えた影響が掘り下げて描かれており、現在においてもセラピストや心理学の研究者にとって重要な参考資料となっています。